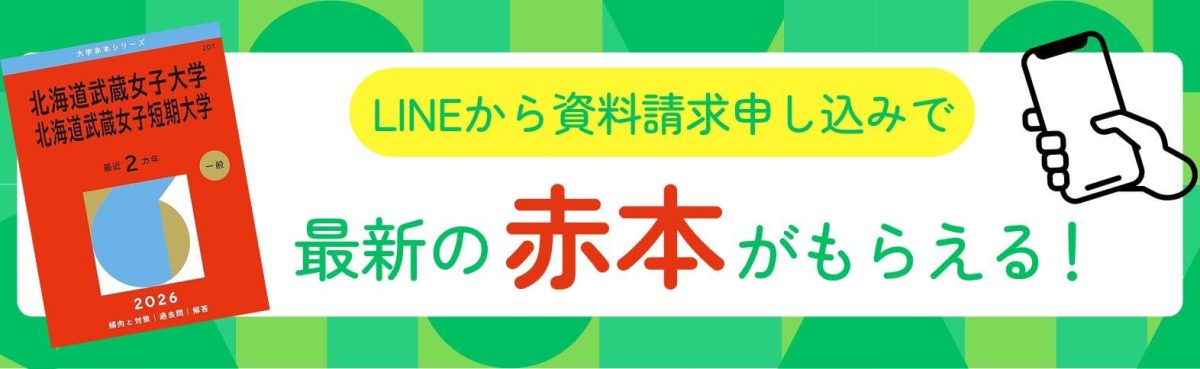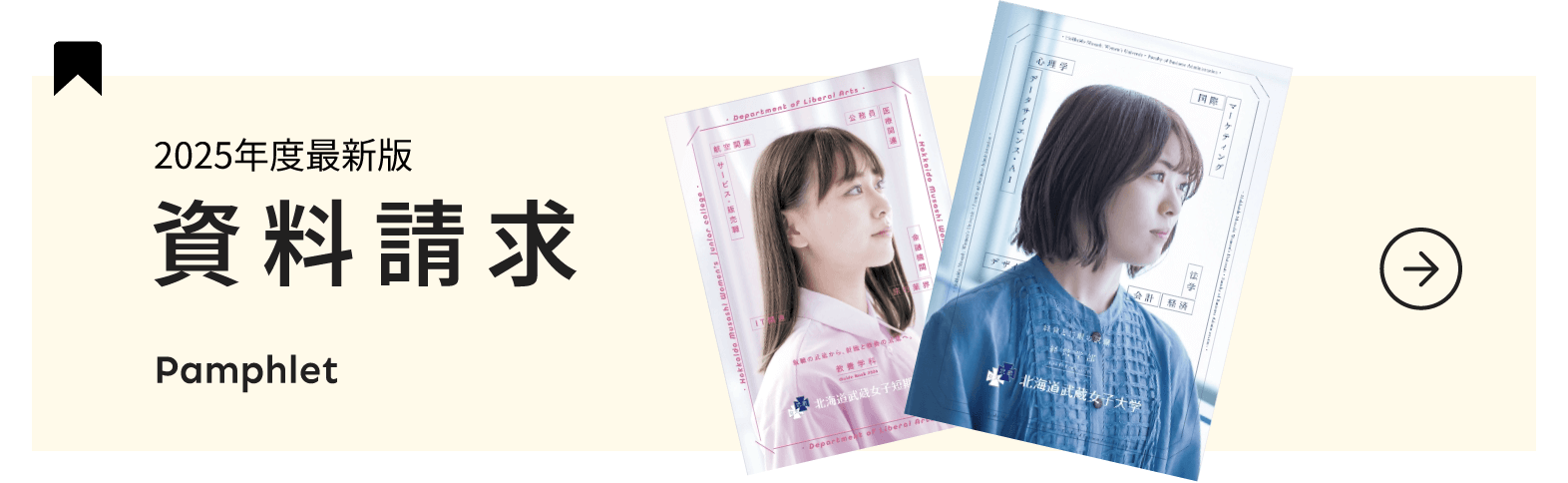北海道武蔵女子大学 経営学部経営学科 入試講評「出題者からのメッセージ」
exam message m42025(令和7)年度 一般選抜
英語 ENGLISH
◆出題の基本方針
経営学部の問題は、「長文読解」「英英対照形式の英文完成問題」「実践的英語読解」「文法・語彙・語法」「語句整序」「自由英作文」から構成されています。北海道武蔵女子大学は世界をフィールドに活躍するグローカル人材の育成を目指しています。そのような人材に求められるのは、短時間で大意を正確に把握する力や、ブロークンな英語でもいいので自分の意見を相手に的確に伝える表現力です。経営学部の問題は、入学後に実践的な英語教育を受ける基礎力の有無を測るための問題です。
◆傾向と対策
「長文読解」はその他の技能にも転移しやすいことから、出題者が重視している分野です。経営学部を志望する受験生の皆さんにはグローカルな社会情勢に日ごろから興味をもってもらいたいという願いを込めて、テーマを選択しています。設問は英文和訳、内容真偽、空所補充等の一般的なものが中心です。
「英英対照形式の英文完成問題」では、同じ内容で書き方の違う2種類の英文が示されます。〔Ⅰ〕の文章内容を要約した〔Ⅱ〕の文章を読み、〔Ⅰ〕と照らし合わせながら〔Ⅱ〕の空所に入る語句を選択肢から選びます。英文の内容は日常的で平易なものです。語彙語法の基礎知識があり文脈が理解できれば、ほとんどの問題は〔Ⅱ〕だけを読んでも解答できます。〔Ⅰ〕は補助的に利用することで短時間での解答が可能となります。
「実践的英語読解」は、グローバル社会で必要となる実践的英語の運用力を試す問題です。大学入学後は、英語を駆使してインターネットで海外の情報を収集する力が必要になります。この問題ではその疑似体験をしていると考えてください。日頃からスマートフォン等で英語のサイトにアクセスして、実践的英語に慣れておきましょう。
「文法・語彙・語法」は、大学入試問題における典型的な4択の問題です。(1)~(5)は空所補充で、(6)~(10)は同義語句選択です。頻出問題を中心に出題していますので、受験用問題集を繰り返し解くのがお勧めです。
「語句整序」も同様に演習問題を繰り返し解くことで対策ができます。基礎的な文法・語法・構文力があれば、日本語を見なくても適切な文章を組み立てられますので、日本語にとらわれすぎずに解くのが良いでしょう。
「自由英作文」では皆さんの表現力を測ります。英語でコミュニケーションをする際には、英文を組み立てるのにあまり時間をかけず、文法などが多少間違っていても、まずは何かを声に出して言ってみるのが大切です。「自由英作文」では「言いたいことが伝わるか」に重点をおいて採点します。何か書けば部分点をもらえる可能性がありますので、必ず解答しましょう。普段から英語で自分の考えを表現することに抵抗がなくなるよう、英作文に積極的に取り組みましょう。
各大問にかける時間配分をあらかじめ決めておけば、時間切れで手がつけられない問題を減らすことができます。また、問題は順番に解く必要はありません。確実に解けるものから解いていくのも一つの方法です。
受験生の皆さんのご健闘をお祈りいたします。
国語 JAPANESE
◆出題の基本方針
本学は、高等学校までの学びを通じて国語に関する基本的な知識を身につけ、大学においては情報活用能力を一層高めるべく主体的に学ぼうとする学生を求めています。
現代はインターネットやデータベースを活用して簡単に情報を入手することができますが、それらを活用するには、①大量の情報から必要な事柄をまとめる力(要約力)、②価値ある情報を選択し問題解決につなげる力 (思考力)、③文章やプレゼンテーションを通じて他者に伝える力(表現力)が必要になります。
本学には、これらの力を養うためのさまざまな授業が用意されています。
本学の学生は、卒業後、社会で幅広く活躍することが期待されています。受験するみなさんには、限られた時間で長文を読み、理解したことを適切に表現する態度を養ってもらいたいと思っています。
◆傾向と対策
以上のことから、問題文はできる限り入学後の学習につながる題材(本年度は社会とのかかわりに関わる問題を出題しました)を採り上げ、選択問題と記述・論述問題の両方を出題しました。受験対策としても、社会的な視野を広げるためにも、インターネットの情報だけでなく、新聞や新書を読んで、幅広い知識と多角的な物事の見方を身につけてください。
本年度の問題文は、第1問の問題文が3000字強、第2問が2500字強でした。読み込むのに時間をかけすぎてしまうと手が回らなくなるのでは、と心配していましたが、ほとんどの受験生が60分間で二つの問題の内容を読み取っていました。
解答の形式は、60~120字の記述問題が8題、私立大学の問題としては記述の分量が多く、空欄が多くなるのでは、と考えていましたが、こちらもほとんど全問解答でした。
実社会において、選択肢が示されたり、答えが一つしか考えられなかったりする問題は、まれです。日ごろから記述問題や論述問題に取り組んで、何をどのように表現すれば、書き手の意図を損なわず、読み手を納得させることができるか、考える習慣をつけましょう。100字を超える解答を書くのは一見大変そうですが、部分的に正しい説明がなされていれば×にはなりませんから、あきらめずにチャレンジしてください。
漢字の問題も、10問出題しています。書類の作成はパソコンを使うことが多くなりますが、メモや伝言、改まった手紙などは、手書きにせざるを得ません。社会人として身につけるべき教養の一つとして、常用漢字は確実に読み書きできるようにしてください。
国語力は大学入学だけでなく、社会で活躍していくためにも欠かせません。以上のポイントを心に留めて、国語力を高めてください。
日本史 JAPANESE HISTORY
◆出題の基本方針
教科書に記述されている基本的な事項について、正確に理解しているか、歴史の流れが押さえられているのかを確認する問題を中心に作成します。また、歴史を俯瞰する広い視野を持っているかを確認するために、時代・分野に偏りなく出題します。さらに史料を読み解いて、歴史の流れの中に史料の記述を正確に位置づけることができているかを確認するために、史料問題も出題したいと考えています。なお、論述問題を含む場合もあります。
◆傾向と対策
大問を4題、設問は50問程度を出題しています。設問形式は記述(一問一答)と選択(空欄補充、正誤判定など)が中心で、論述を含む場合があります。政治史を中心に外交史、社会経済史、文化史などの全分野を出題対象としており、時代についても原始時代から現代まで対象としています。また、いくつかの時代にまたがって一つのテーマを追う通史的問題も出題されることがあります。さらに、大問のうち1題が史料問題になることもあります。
時代、分野に偏りなく出題されますので、不得意な時代・分野をつくらないように、全範囲にわたって学習しておく必要があります。難易度については教科書中の基本事項が大部分を占めますから、まずは教科書を精読し、基本事項を確実に理解することが肝要です。文章の正誤判定などに対応するためにも、教科書を使って歴史の大筋・流れを押さえ、史実の背景や因果関係を丁寧に把握しておくことが不可欠です。また、用語集を使って用語の知識を充実させることも大切です。歴史的背景を理解できているかを確認するために、論述問題を出題することがありますので、教科書の基本事項に加え、さらに深い知識も必要となります。
史料については、初見のものも出題されますので、学習時には、史料を必ず参照し、日頃から史料に慣れておくことが大切です。記述問題がありますので、用語については教科書に記されている正しい漢字で書けるよう、正確に記憶しておく必要があります。
受験生の皆さんのご健闘をお祈りいたします。
世界史 WORLD HISTORY
◆出題の基本方針
歴史という学問はすぐに実用に役立つものではありませんが、過去から現在までの変化の道筋を辿ることによって、今私たちが直面している諸問題を解決する糸口にすることはできます。グローバル化が進む21世紀に生きる私たちには、ものごとを地球規模で考えていくことが求められています。その意味で、世界史を学ぶことは国際社会を生きるための素地を身につけることにもつながるでしょう。それぞれの国々、地域の人々がどのような社会でどのような特色ある文化を形成してきたのかを知ることは、現在の自分の立ち位置を知るとともに未来を考えるヒントにもなるはずです。
こうした観点から入学試験では、原則として教科書に記述されている範囲から出題し、いたずらに無意味なことを問う難問や奇問は出題しない方針ですが、歴史の流れや展開をしっかりと理解しているかどうかを試していきたいと思います。そのため、基本的事項や人物名、年号の暗記にとどまらず世界全体の文脈の中で社会がどのように変化し、物事がどのように展開してきたのかを理解できるように、教科書をしっかりと学習してください。また、地域や時代を限定することなく、広い視野で、世界各地のこと、各時代のことを勉強し、歴史上のひとつひとつの事柄が他の事柄とどのように関連しているのかをよく理解するように努めてください。
◆傾向と対策
例年、大問題を4題出題し、教科書の内容や範囲にしたがって、世界各地の歴史を時代的に地理的にもできるだけ偏りのないように出題しています。出題形式は、記述式と論述式からなり、記述式の問題は、人物、事件、制度、年代などの基本事項を問い、それらが歴史の流れや展開の中でどのような意味をなしているのか、広い視野から把握し理解しているかどうかを問うことを目的としています。論述式の問題は、特定の地域や時代に関する重要事項から出題し、その歴史事項や因果関係について正確に理解しているのか、そしてそれを簡潔な文で説明する力を持っているかを試そうとしています。時代、地域を問わず政治史、文化史、経済史など幅広い分野から出題しますので不得手な領域を作らないよう、日頃から知的好奇心を持ち、コツコツと学ぶことを心掛けてください。
2025年度入試は、古代中央アジアとイスラーム勢力、西ヨーロッパの封建社会、近世のイギリス、清朝の終焉と近代中国に関する問題を出題しました。
問題の大部分は基本的な知識を問うものですから、教科書を精読し、太字で書かれた事柄を正確に理解し、覚えるようにするとよいでしょう。ただし、自分の使っている教科書には載っていなくても、他のいくつかの教科書に出ている事柄についても出題しますので、用語集や参考書などで補う勉強をしておくことが必要です。
世界史を選択される皆さんは、世界規模で展開する社会経済の大きな流れを押さえることで、入学後に受講する講義の理解がより一層深まるだけでなく、個別の問題を深く研究する際にも広い知識が役に立つことでしょう。
受験生の皆さんのご健闘をお祈りいたします。
地理 GEOGRAPHY
◆出題の基本方針
系統地理的な考察,地誌的な考察によって習得した知識や概念を活用し、「社会的事象の地理的な見方・考え方」を働かせながら思考・判断し、解答する問題を出題します。
大問構成については、現代世界の系統地理的考察に関する出題(「自然環境」「資源、産業」「交通・通信、観光」「人口、都市・村落」「生活文化、民族・宗教」から3つの項目)を3題(配点60%程度)、現代世界の地誌的考察に関する出題(1~2の地域)を1題(配点20%程度)、地域調査・国土像の探究に関する出題を1題(配点20%程度)とし、解答形式については、多肢選択肢を中心としながら、30字~60字程度の論述も4~5問程度出題します。
◆傾向と対策
①知識・技能
地球上で見られる様々な地理的諸事象(規則性・傾向性や、諸地域の地域的特色や課題など)についての基本的な知識を理解しているか、また、地図や統計、写真など、地理的諸事象が示された資料から適切に情報を読み取る技能が身に付いているかを問います。
多くの問題が資料から展開されていきますので、普段の授業や学習から、「情報全体の傾向性を見出すこと」「目的に応じた情報を選ぶこと」「複数の情報を見比べたり結び付けたりすること」などを心がけてください。それとともに、探究的な学習の中で、明らかにしたい課題(問い)を自ら設定し、必要な情報を収集する活動や、収集した情報を表に加工したり、地図化・グラフ化したりしてまとめる活動を行うことも大切です。
②思考・判断・表現
地球上で見られる様々な地理的事象の意味や意義、特色や相互の関連などについて、知識を活用し、多面的・多角的に考察する力や、考察したことを論理的に説明する力が身に付いているかを問います。
暗記した知識を単純に再生する出題(一問一答式や空欄補充問題)は少ないので、普段の授業や学習から、「なぜそのような規則性、傾向性を示すのか」「そこはどのような場所なのか」「なぜ そのような影響を受けているのか」「そこはそれ以外の場所とどのような関係をもっているのか」「なぜそのような結び付きをしているのか」「なぜこの場所はそのようになったのか」「どのような地域にすべきか」といった問いを通して地球上で見られる様々な地理的事象を捉え、考察、構想することを心がけてください。それとともに、考察、構想したことを他者と議論(意見交換)する活動を行うことも大切です。
受験生の皆さんのご健闘をお祈りいたします。
政治・経済 POLITICS&ECONOMIC
◆出題の基本方針
私たちの「政治・経済」の問題作成にあたっては、現代社会を構成する両輪である政治と経済の分野について、皆さんのバランスの取れた理解度を測りたいと考えています。特に、日々の生活と密接に関わり、その動向の理解が不可欠である経済分野への深い洞察を促すため、政治分野から1問、経済分野から2問、合計3問の構成としています。
出題内容は、あくまで高校の教科書で扱われる基本的な事項や重要な事柄を核としており、高校での学習範囲を逸脱することはありません。これは、皆さんが学校での日々の授業や探究活動を大切にしてきたかを確認するためのものです。
私たちは、単なる用語の暗記に留まらない、事象の背景や意味を正しく理解し、それを自分の言葉で的確に表現できる力を特に重視しています。そのため、知識の有無を問う空欄補充や選択問題に加えて、思考の過程が問われる記述問題も出題し、皆さんの深い理解度を確認することを意図しています。知識の量を競うような難問・奇問は避け、基本的な知識をいかに深く、多角的に理解しているかを問う良質な問題作成を心がけています。
◆傾向と対策
本学の入試問題は、単なる用語の丸暗記だけでは対応が難しいという特徴があります。これは、政治・経済・社会の仕組みや制度が、歴史の中でどのように変化し、現代においてどのような役割や課題を持つのかを、体系的に理解しているかを問うためです。
政治や経済の出来事は、一つの要因だけでなく、様々な要因が複雑に関わり合って動いています。したがって、一つの事象の裏にある関連性を見つけ出す分析力や、筋道を立てて説明する論理的な思考力が求められます。実際の試験でも、大問ごとに設定されたリード文をしっかり読解し、空欄補充、選択問題、そして30字~120字程度の記述問題といった多様な形式の設問に答える能力が必要です。
この傾向に対応し、合格を勝ち取るためには、以下の学習を強く推奨します。
1. 因果関係を探求する学習
教科書や資料集を読む際には、常に「なぜこの制度ができたのか?」「この出来事は何に影響を与えたのか?」と自問し、出来事や制度の背景・影響・原因と結果の関係を深く理解することが不可欠です。この「なぜ?」を繰り返す学習が、応用力と思考力を養います。
2. 記述力を意識した日常学習
教科書に出てくる重要な用語や歴史的な出来事について、「これは、こういう目的で、こういう仕組みのことだ」というように、30~50字程度の短い文章で要約・説明する練習を日頃から行いましょう。このアウトプットの練習が、思考を整理し、記述問題への即応力を飛躍的に高めます。
3. 時事問題と教科書知識の往復学習
日々の新聞やニュースに触れて現代社会の動きを追うことは重要ですが、それに加えて、その出来事が「教科書のどの単元の、どの知識と関連しているか」を意識するようにしてください。時事的な知識を、教科書で学んだ普遍的な知識の体系に位置づけることで、知識は立体的で忘れにくい実践的なものになります。
以上の点を意識して学習に励み、皆さんの持つ力を十分に発揮されることを期待しています。
数学 MATHEMATICS
◆出題の基本方針
短期大学と同様に大問3問の構成でした。問題Ⅰ、Ⅱの出題範囲は数学Ⅰ・Aで必須とし、問題Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵは選択問題で、それぞれ数学Ⅰ・A、数学Ⅱ、数学B(数列)、数学C(ベクトル)からの出題(4題から1題選択)でした。
問題Ⅰは小問集合形式で小問(6問)を数学Ⅰ・A全般にわたって幅広く出題し、基本事項の理解度を問う答えのみを求める形式でした。
問題Ⅱ以降は記述式とし、教科書の理解度と正確な計算力が身に付いているかどうかを問う内容で、結論に至るプロセスから思考力・表現力を含め評価・採点しました。
問題Ⅱは2次関数、2次方程式・不等式の問題で、基本的な理解度と論理的思考力を見ました。
問題Ⅲはさいころの確率の問題でしたが、余事象や倍数を取り扱う力が必要な応用問題でした。
問題Ⅳは円と直線の位置関係を問う問題で、教科書や問題集でもよく取り上げられる内容でした。
問題Ⅴは等差数列が題材でした。問題文の集合表現により、見かけが難しく感じたかもしれません。
問題Ⅵはベクトルの内積を利用して外心を調べる問題で、入試ではよく問われる内容でした。
今回の入試は、数学Ⅰ・Aの基本を押さえ、数学Ⅱ、数学B、数学Cの範囲の得意分野を解答できた受験生は実力を発揮できたと思います。
◆傾向と対策
2026年度入試については昨年同様に大問3題の解答となります。出題構成も昨年同様、問題Ⅰが数学Ⅰ・Aの小問集合(答えのみ)。問題Ⅱは数学Ⅰ・Aの記述式となり、ここまでが必須問題です。数学Aの出題範囲は昨年と同様、場合の数と確率、数学と人間の活動(整数の性質に関する部分)です。問題Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵはそれぞれ数学Ⅰ・A、数学Ⅱ、数学B(数列)、数学C(ベクトル)からの出題で、4題から1題選択(記述式)となります。全体の分量や難易度は例年と同程度と考えてください。
出題される問題は教科書に掲載されている問題(例題のレベル)が中心です。高校の授業を大切にして、まず基本事項の理解に取り組んでほしいと思います。教科書の練習問題を解きながら公式を正しく使い正確に計算できるようにトレーニングしてください。記述式では各分野の融合問題など数学の総合的な力が試される場合もあるので、教科書の章末問題や学校で使った問題集で実力を養成してください。また、問題文が一見難しいように感じた場合も、具体的な例を考えると比較的基本的な内容であることに気が付きます。最後まで完答できなくても (1)、(2)くらいまでは教科書の基本レベルですので、決してあきらめずに取り組むことが大切です。このように高校の授業(教科書)をきちんと理解していれば解ける問題を出題しますので、日ごろの努力が実を結ぶように祈っています。
情報 I INFORMATION I
◆出題の基本方針
本学の一般入試に「情報」が加わった初めての入試となりました。本学 経営学部が求める学生像では、ビジネスの世界で活躍するために必要な基礎学力、思考力・判断力・表現力を挙げていますが、コンピュータを駆使し、データを活用する能力は、これらの力を身につけるための土台となります。
本科目では、皆さんが高等学校で学ぶ「情報 I」の4つの領域、すなわち「(1)情報社会の問題解決」「(2)コミュニケーションと情報デザイン」「(3)コンピュータとプログラミング」「(4)情報通信ネットワークとデータの活用」の基本的な内容を、教科書に準拠した形で幅広く出題します。これらは、経営学部での学び、特にこれからの社会で重要になるデータサイエンスやAIの分野で重要であり、皆さんがデータを活用し、AIと協働しながら活躍するための、情報に関する確かな知識と思考力を問う内容です。
◆傾向と対策
昨年度の出題
(1)情報社会の問題解決の分野からは、問題Ⅰを出題し、知的財産権に関する知識などを問いました。
(2)コミュニケーションと情報デザインでは、問題Ⅱと問題 Ⅲで、コンピュータにおけるデジタルデータの扱いやその表現方法を問いました。
(3)コンピュータとプログラミングでは、データ構造とアルゴリズムの基礎理解を問う問題Ⅴを出題しました。
(4)情報通信ネットワークとデータの活用では、情報通信ネットワークの仕組みを問う問題Ⅱ、更に、統計データをまとめたグラフや表から情報を読み解き、背景にある理由を読み解く力を問う問題Ⅳを、新聞のコラムより抜粋して出題しました。
全体として、基本問題を幅広く出題しましたが、知識を問うだけでなく、データから論理的に思考し、判断を下す力を評価する問題も含まれています。なお、昨年度に限り問題Ⅵとして旧課程「情報Ⅰ」の範囲も含む選択問題を出題しましたが、今後は新課程に準拠した出題となります。
対策
引き続き「情報Ⅰ」の4つの領域から、基本事項の理解度を問う問題を広く出題します。特定の分野に偏りなく、満遍なく学習することが大切です。まずは教科書をじっくりと読み込むことから始めてください。専門用語の意味を正確に理解し、語句や概念がどのように関連しているのかを把握し、学んだことを整理しておくことが重要です。プログラミングについては、特定の言語に縛られるのではなく、コードの意味をしっかり理解し、コードでの表現方法と、記述的な説明との対応を意識して学習しましょう。また、教科の学習に留まらず、日常生活の中でデータをどのように活用し、問いの答えを得ているのかに興味を持つ姿勢も非常に重要です。皆さんがスマートフォン等でニュースを読む際、その裏側にある理由とデータの関係について考えてみましょう。
皆さんがこれまでに培ってきた「情報」に関する知識を、大学での学びにつなげられることを期待しています。