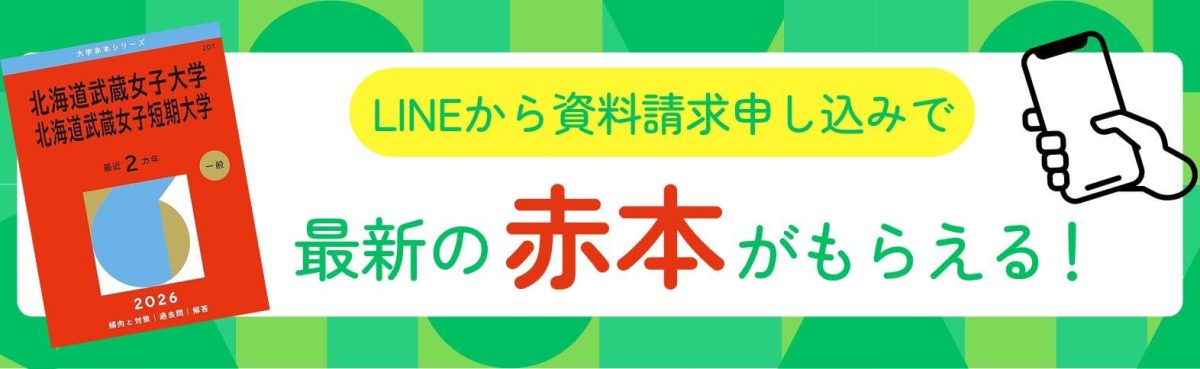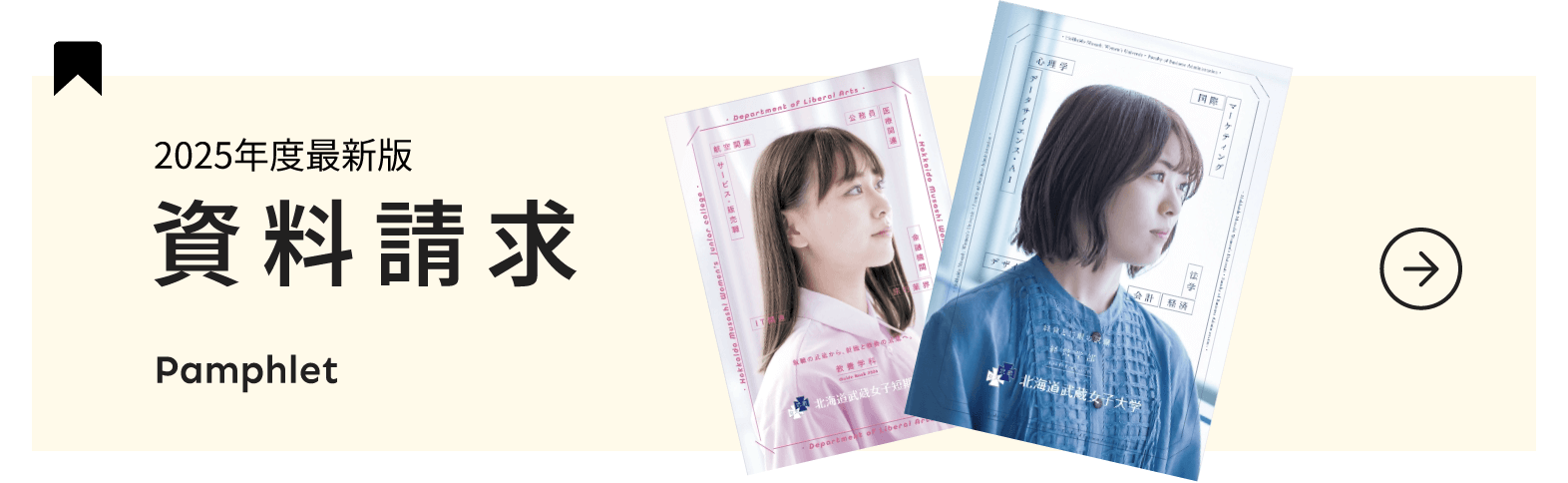北海道武蔵女子短期大学 入試講評「出題者からのメッセージ」
exam message m22025(令和7)年度 一般選抜【前期日程】
英語 ENGLISH
◆出題の基本方針
英語の問題は、「長文読解」「文法・語彙・語法」「語句整序」「会話文」「英作文」から構成されています。皆さんが北海道武蔵女子短期大学に入学してから、しっかりと授業についてこられる基礎的な力を身に付けてきたかを把握するための問題です。
近年は英語での発信力が重視されてきていることから、自由英作文でアウトプット力を測ります。リスニングとスピーキングはありませんが、どちらもコミュニケーションでは欠かせないスキルであることから、入学後や卒業後の進路を見据え、4技能をバランスよく学習することが非常に重要になります。
特にイングリッシュ・スタディーズ・プログラム(ESP)では、①基礎から応用までの4技能を学ぶ「ESP科目」と②実践的な「履修指定科目」を中心とする科目群を学ぶことになりますので、その土台となる基礎的、かつ総合的な英語力を鍛えてきてもらいたいと思います。以上より、ESPには、英語の基礎的な科目や将来のキャリアに繋がる英語系の実践科目が配置されていますので、どのコースにおいても、まずは高校までの基礎をしっかりと固めることが求められます。
試験の難易度は実用英語技能検定の準2級から2級レベルと言えます。
◆傾向と対策
「長文読解」は、様々なジャンルから出題されますが、いずれも話の流れをどの程度読めているかを見ることを出題の中心としています。多少高度な設問や記述式解答を求める設問も含んでおり、英語の理解力を総合的に測ります。入学後は様々な分野の英文を読むことになりますし、リーディングはその他の技能にも転移しやすいことから、出題者も重視している分野です。物語から社会情勢まで様々なことに日ごろから興味を持ってもらいたいという気持ちを込めて出題しています。
外国語の学習に欠かせないのが語彙・文法・語法の知識です。語彙の基本的な用法やニュアンスについて、また基礎的な文法の知識があるかも問われます。なんとなく話が理解できればよいというだけでなく、日ごろから正確な文法や語彙の使用を心掛けることは、コミュニケーションをスムーズに行うためにも重要です。
会話文では、口語表現や会話の自然な流れを読み取る力が試されます。普段から話者の意図を気に留めながらダイアローグなどを読むことを心掛けるとよいでしょう。入学後のスピーキングやリスニング系の科目をはじめ、海外研修などにも役に立ちます。
英作文の問題は、語彙・文法・語法・構文力等を総合的に測る問題のほかに、自分の言葉で考えを発信する自由英作文があります。普段からこの日本語はどのように英語で表現できるかを考える癖をつけることや、自分の意見を伝えるために、ある程度まとまった英文を書く習慣をつけておくとよいでしょう。いずれも高校までの授業を大切にして、しっかり取り組むことで対応できる力がつきます。
受験生の皆さんのご健闘をお祈りいたします。
国語 JAPANESE
◆出題の基本方針
本学の学生は、卒業と同時に、すぐに社会に飛び出していく場合が多くあります。その際には実務的な能力も求められますが、そうしたものを最大限に活かす基盤(ベース)として、日本語を理解する力と、自分で考えたことを伝える表現力が欠かせません。より具体的に言えば、他者の文章を正確に読み取る力、そして自分で報告書や企画書をまとめる力、あるいは人前でしっかりと物事を順序立てて、効果的に伝えるプレゼンテーション力です。
そのような、社会に求められる学生を育てるという本学の方針から、入試を受けるみなさんには、集中力をもって、ある程度まとまった分量の問題文にしっかりと向き合う態度を養っておいてもらいたいと思っています。出題の基本方針としては、社会的な問題に幅広く目を配った題材を取り上げ、それをみなさんが適切に読み取り、解答を文章化することができるかを測ることを重視しています。
◆傾向と対策
以上のことから、みなさんには、日頃から、優れた日本語の著作に触れておいてほしいと思っています。好きな小説やエッセイのほか、社会的な視野を広げてくれる、新書などを読む習慣をつけておくことをおすすめします。
本学の国語の問題は、限られた時間内にそれなりの分量の問題文を読み、ある程度の文字数の解答を求める傾向にあります。まずは、いろいろなジャンルの本を読み、一章を80字程度で要約する練習を始めてみましょう。入試の解答時間を考えると、自分がどのくらいの時間で、どのくらいの分量が読めるのか、そしてどのくらいの文字数が書けるのかを知り、訓練しておくといいかもしれません。本番では、あきらめることなく、できる限り文字数を満たすように心がけてください。
また、漢字の読み書きは毎年必ず出題されます。小学校から高校までに習った漢字について、毎日少しずつでもいいので、見直しておきましょう。間違えた字だけをチェックして、復習すればいいのです。ほかに、慣用句を含む「言葉の意味」を問うことも多くあります。意味の分からない言い回しに触れたら、放っておかずに調べる癖をつけておくとよいでしょう。
以上のことは、入試に限らず、今後のみなさんの人生のためにも役立つことと思います。みなさんにお会いできるのを楽しみにしています。
日本史 JAPANESE HISTORY
◆出題の基本方針
教科書に記述されている基本的な事項について、正確に理解しているか、歴史の流れが押さえられているのかを確認する問題を作成します。また、歴史を俯瞰する広い視野を持っているかを確認するために、時代・分野に偏りなく出題します。さらに史料を読み解いて、歴史の流れの中に史料の記述を正確に位置づけることができているかを確認するために、史料問題も出題したいと考えています。
◆傾向と対策
例年、大問を4題、合計50問の設問を出題しています。設問形式は記述(一問一答)と選択(空欄補充、正誤判定など)が中心になっています。政治史を中心に外交史、社会経済史、文化史などの全分野を出題対象としており、時代についても原始時代から現代まで対象としています。また、いくつかの時代にまたがって一つのテーマを追う通史的問題も出題されることがあります。さらに、大問のうち1題が史料問題になることもあります。
時代、分野に偏りなく出題されますので、不得意な時代・分野をつくらないように、全範囲にわたって学習しておく必要があります。難易度については教科書中の基本事項が大部分を占めますから、まずは教科書を精読し、基本事項を確実に理解することが肝要です。文章の正誤判定などに対応するためにも、教科書を使って歴史の大筋・流れを押さえ、史実の背景や因果関係を丁寧に把握しておくことが不可欠です。また、用語集を使って用語の知識を充実させることも大切です。
史料については、初見のものも出題されますので、学習時には、史料を必ず参照し、日頃から史料に慣れておくことが大切です。記述問題がありますので、基本用語については教科書に記されている正しい漢字で書けるよう、正確に記憶しておく必要があります。
受験生の皆さんのご健闘をお祈りいたします。
世界史 WORLD HISTORY
◆出題の基本方針
歴史という学問はすぐに実用に役立つものではありませんが、過去から現在までの変化の道筋を辿ることによって、今私たちが直面している諸問題を解決する糸口にすることはできます。グローバル化が進む21世紀に生きる私たちには、ものごとを地球規模で考えていくことが求められています。その意味で、世界史を学ぶことは国際社会を生きるための素地を身につけることにもつながるでしょう。それぞれの国々、地域の人々がどのような社会でどのような特色ある文化を形成してきたのかを知ることは、現在の自分の立ち位置を知るとともに未来を考えるヒントにもなるはずです。
こうした観点から入学試験では、歴史上のひとつひとつの事柄が、世界全体の文脈の中でどのような意味をなしているのか、広い視野から把握し理解する力を試していきたいと思います。政治史、経済史、文化史など幅広い分野からの出題になりますが、作問者の主眼は基本事項の理解度を確認することですので、原則として教科書に記述されている範囲から出題し、いたずらに無意味なことを問う難問、奇問を出すことはありません。日ごろから知的好奇心を持ち、コツコツと学ぶことを心掛けてください。
◆傾向と対策
例年、大問題を4題出題し、総解答数は50問程度としています。出題形式は記述式が中心で、リード文中の空欄を埋めるものと、下線部に関連する事項を問う問題が大半です。年によっては、解答用紙1行程度の字数の論述問題を出題することがありますので、歴史事項や因果関係を簡潔な文で説明できるよう書く練習もしておいてください。時代、地域を問わず政治史、文化史、経済史など幅広い分野から出題しますので不得手な領域を作らないよう、まんべんなく学習しましょう。
2025年度入試は、ギリシア世界、アメリカの独立と南北戦争、明代中国、近現代の南アジア・東南アジアに関する問題を出題しました。
問題の大部分は基本的な知識を問うものですから、教科書を精読し、太字で書かれた事柄を正確に理解し、覚えるようにするとよいでしょう。ただし、自分の使っている教科書には載っていなくても、他のいくつかの教科書に出ている事柄についても出題しますので、用語集や参考書などで補う勉強をしておくことが必要です。
世界史を選択される皆さんは、古今東西の歴史の大きな流れを押さえることで、入学後に受講する講義の理解がより一層深まることでしょう。
受験生の皆さんのご健闘をお祈りいたします。
地理 GEOGRAPHY
◆出題の基本方針
地理の出題は、教科書に記述されている基本事項に基づき、地理学の基礎知識や地理的思考力、情報やデータの解釈と分析能力、現実社会への応用力や問題解決能力などを総合的に評価することを目指しています。
◆傾向と対策
出題の傾向としては、地理の基礎知識を問う問題だけでなく、地理的な情報分析能力や問題解決能力を問う問題を出題します。また、複合的な要素をふまえて、論理的に情報を整理する能力が問われます。加えて、社会情勢や環境問題などへの関心や理解をふまえて、地理に関する最新の情報やトピックについても問われることがあります。
具体的には、以下の評価項目にしたがって対策をしてください。
1.情報を調べまとめる技能の評価
地理に関わる諸事象に関して、世界の生活文化の多様性や、防災、地域や地球的課題への取組などを理解するとともに、地図や地理情報システムなどを用いて、調査や諸資料から地理に関する様々な情報を適切かつ効果的に調べまとめる技能を評価する問題を出題します。初見資料が出てきますが、既習事項と結び付けて、落ち着いて解答してください。
2.地理的思考力の評価
地理に関わる事象の意味や意義、特色や相互の関連を、位置や分布、場所、人間と自然環境との相互依存関係、空間的相互依存作用、地域などに着目して、概念などを活用して多面的・多角的に考察したり、地理的な課題の解決に向けて構想したりする力や、考察、構想したことを効果的に説明したり、それらを基に議論したりする力を評価する問題を出題します。
3.現実社会への応用力の評価
地理に関わる諸事象について、よりよい社会の実現を視野にそこで見られる課題を主体的に追究、解決しようとする力を評価する問題を出題します。
地理の学習においては、地名や用語を暗記するのではなく、この事象がどうして起こっているのか、どのような場所で起こっているのかなど、日頃から地図や統計資料を見ながら、さまざまな事象と結び付けて考えながら学習する習慣を付けてほしいと思います。
受験生の皆さんのご健闘をお祈りいたします。
政治・経済 POLITICS&ECONOMIC
◆出題の基本方針
私たちの「政治・経済」の入試問題は、皆さんが社会の基本的な仕組みをどれだけ理解しているか、そして現代社会で起きている出来事にどれだけ関心を持っているかを確認することを目的としています。そのため、「政治分野」から1問、「経済分野」から1問という基礎的な知識を問う大問に加え、現代社会への関心を問う「総合問題」を1問加えた、合計3問構成としています。
出題内容は、すべて高校の教科書に記載されている基本的な事項や重要な事柄が中心です。これは、高校での日々の授業を大切にし、基礎を固める学習が何よりも重要であるというメッセージでもあります。
出題形式については、複雑な論述を求めるのではなく、基本的な用語や制度の名称、その意味を正確に覚えているかをまっすぐに問いたいという意図から、空欄補充問題や選択問題を中心としています。まずは基本知識をしっかりと定着させているかどうかを確認することを、私たちは重視しています。
◆傾向と対策
短期大学の「政治・経済」で合格点を取るためには、複雑な応用問題に頭を悩ませるよりも、「教科書の基本知識を徹底的に定着させること」と「日々のニュースに関心を持つこと」、この二つが最も重要で効果的な対策となります。
特に、本学の入試で最大の特徴と言えるのが、大問の一つとして出題される「総合問題」です。ここでは、最近1~2年のニュースで頻繁に報道された時事的なキーワード(例えば、過去には「オーバーツーリズム」「こども家庭庁」「ALPS処理水」などがテーマとなりました)に関する知識が直接問われます。この大問が、合否を分ける大きなポイントになります。
以上の傾向を踏まえ、合格を勝ち取るための具体的な学習法を以下に示します。
1.教科書と用語集の反復学習を徹底する
まずは、高校で使っている教科書と用語集を隅々まで読み込み、特に太字で書かれている重要語句は、見てすぐに意味が言え、漢字で正確に書けるレベルまで仕上げてください。人名、法律名、制度名、歴史的な出来事など、基本的な知識の正確な暗記が、政治分野・経済分野の大問で確実に得点する力になります。
2.「時事問題ノート」を作成し、ニュースを習慣にする
これが「総合問題」への最も有効な対策です。毎日5分でも良いので、テレビやインターネットのニュースに触れる習慣をつけましょう。そして、「これは試験に出るかもしれない」と感じた政治・経済・国際問題に関するキーワードや人名をノートに書き出し、その意味を簡単に調べてメモしておくのです。この日々の積み重ねが、入試本番で大きな力となります。
求められているのは、難しい分析力や論理的思考力よりも、社会の基本ルールと「今」を知ろうとする誠実な学習姿勢です。上記の2点を着実に実行し、自信を持って試験に臨んでください。
受験生の皆さんのご健闘をお祈りいたします。
数学 MATHEMATICS
◆出題の基本方針
全般にわたって幅広く出題し、基礎・基本をきちんと身に付けているか、さらに応用的な問題に対して、知識・理解だけでなく、数学的・論理的に粘り強く解き、解答に表現する力を身に付けているかを問う問題です。
大問3問の構成で、1問目と2問目は、必須問題で、出題範囲は「数学Ⅰ・数学A(場合の数と確率、整数の性質に関する部分)」となっています。また、3問目は、「数学Ⅰ・数学A(場合の数と確率、整数の性質に関する部分)」、「数学Ⅱ」、「数学B(数列)」、及び「数学C(ベクトル)」の4題から1題の選択です。
内容については、1問目は、小問数6問で結果のみを解答する形式、2問目は、2次関数の頂点やx軸との関係、最大値、確率との関係など、3問目は、数学Ⅰ・数学Aが三角比(三角形への応用)、数学Ⅱは三角関数(グラフと方程式、)、数学Bは数列(等比数列とその和)、数学C(位置ベクトル・内積等)から、記述式の頻出・融合問題となっています。
◆傾向と対策
2026(令和8)年度入試については、昨年度同様、出題数は大問3問構成を予定しており、1問目と2問目は必須問題で、出題範囲は「数学Ⅰ・数学A(場合の数と確率、整数の性質に関する部分)」となっています。また、3問目は、「数学Ⅰ・数学A(場合の数と確率、整数の性質に関する部分)」、「数学Ⅱ」、「数学B(数列)」、及び「数学C(ベクトル)」の4題から1題を選択することになります。
また、出題形式については、1問目は、数題の小問を結果のみの解答を求める形式を予定しており、2問目と3問目は、記述式で解答に至るまでの過程から、数学的・論理的に粘り強く解き、表現する力が身に付ついているかを問われることになりますので、普段からそのことを踏まえて演習に取り組むことが大切です。
全体の分量は例年並みで、教科書を中心に公式の意味を理解し、的確に使えるようにするなど、基礎・基本をきちんと身に付けるとともに、例題など標準的な問題をしっかり理解し、章末問題などの応用問題にも積極的に取り組むなど、広く地道な学習で十分対応できる問題を想定しており、過去問題に取り組むことも大切と思います。
受験生の皆さんの日頃の努力が実を結ぶことを期待しています。